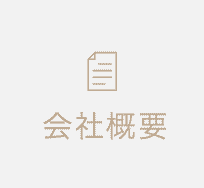こんにちは、ナレッジ推進室 漢方養生スタイリスト「福田 貴之」です。
今月のコラムはまもなく7月に入りますので、暑邪(しょじゃ)についてお話をしたいと思います。
梅雨のジメジメと夏に向かっての気温の上昇は私たちの健康や肌の状況を悪化させる可能性が生まれます。
「六淫(りくいん)」の話は過去したことがあると思いますが、漢方医学では外因(主に気候による体調変化)により病気を発症させる要因になるものを「六淫」といいます。
人はこの季節による気候変動に大変影響を受けやすいといわれています。
過去であれば春は「風邪(ふうじゃ)」。
秋であれば「燥邪(そうじゃ)」など。

そしてこれから訪れる7月は梅雨により、暑くなる時季でもあります。
暑さによって起こる現象である「発汗」などによって、「暑邪」が私たちに襲い掛かります。
再度6つの六淫について少しだけお話ししましょう。
私たち人間は6つの気候変動に影響されるといわれています。
「風(ふう)」「寒(かん)」「暑(しょ)」「湿(しつ)」「燥(そう)」「火(か)又は熱(ねつ)」6つの気候を「六気(ろっき)」とよびます。
この六気が大きく変化すると「邪気」が加わり、六淫に変化するといわれています。
今回はその中で「暑邪」の養生についてお話ししたいと思います。
「暑邪」は夏の暑い時季の発汗によりエネルギー源である「気」と潤いの元でもある「陰」が奪われやすくなります。
暑邪は、高熱、顔面紅潮、大量発汗、口渇などの激しい熱症状を起こします。

現代でいえば「熱中症(熱射病・日射病)」もこの「暑邪」に当てはまると考えます。
そう考えると熱中症は死亡事故にも繫がり、現代の気温上昇を考えると怖い症状でもありますね。
ではどうすれば「暑邪」から守れるかを見ていきましょう。
夏の養生として五臓でみると「心(しん)」と「脾(ひ)」です。
「心」は五行で季節は「夏」味は「苦味」色は「赤」です。
食養生でいえば、まずは「夏」は身体が暑くなりますので冷やす食材を選びます。
夏野菜は身体の熱を下げる効果が期待できるものが多いので、ナスやキュウリ、トマトなどを取り入れましょう。
また味は「苦味」です。
ゴーヤや春菊など苦みのある野菜を食べます。
そして色は「赤」です。
赤い食材であるトマトや梅干しなどを摂り入れましょう。

そしてもう一つ「脾(ひ)」です。
五行で季節は「土用(季節の変わり目)」で体調を崩しやすい気候です。
体力を養うために栄養があるものをしっかり食べます。
自然な甘みがあり、黄色い食材を摂りたいので玄米やカボチャ、トウモロコシなどを取り入れましょう。
ちなみに味は「甘い」、色は「黄」です。
日本には四季があり、温暖化などで季節は狂い始めてはいますが、「旬」の食材を摂ることが私達の身体のためになっていると考えます。
暑い時季を元気に乗り切るためにも「旬」の食材を意識して摂ってみませんか。
以上です。
本日もお読みいただきありがとうございました。
ナレッジ推進室 漢方養生スタイリスト福田 貴之でした。