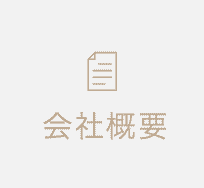灼熱の砂漠を、塩や水の入った重い甕(カメ)を背中に乗せて力強く歩いていくラクダ。
どれだけ荷物を積んでもびくともしません。
頼りになる存在です。
そこに風が吹いてきました。
その風に乗って1本のワラが飛んできて荷物の上に乗りました。
その途端、強靭なラクダの背中が折れて倒れてしまうという英語の諺があります。
あんなに軽いワラ1本があの強いラクダを倒してしまうなんて…
その光景をイメージすると強靭なラクダと吹けば飛ぶような一本のワラの対比がなんともミスマッチな感じがします。

我慢の限界
ある物事が耐える限度を超えてしまうきっかけとなったのは小さなことだったということありますね。
それまで耐えられていたものが、ほんのわずかなことで限界を超えてしまうというこのラクダとワラの例えは、日常生活でもよく起こります。
あなたの周りにもいませんか?
何があっても強く生きている (ように見える)強い人。
その人自身もみんながそう感じているだろうことを察して、期待に応えなければと弱音も吐けなくなっているような人。
強靭なラクダさん〜
弱音も愚痴も吐かずに毎日頑張っていませんか。
大丈夫ですか?
思い出してください。
弱音と愚痴は全く違います。

弱音は
自分の心に正直であることで、窮地にいる自分の心の声をそのまま口に出すことで息抜きできます。
「疲れが溜まっている」「迷いが多くて辛い」「体力なくて頑張れない」ただ話を聞いてくれる、そういう信頼できる相手が周りにいてくれるとありがたいです。
愚痴は
自分の窮状を誰かあるいは何かのせいにして相手を責め否定し不満を言うこと。
「上司は理解がない」「私の気持ちを誰も理解してくれない」「こんな日本の社会はダメだ」
これを聞いてる方も嫌な思いになるし、口に出せば出すほど自分が惨めになりますね。
確かに
何が起きても動じない姿は強くて立派。
だけど大木のようにまっすぐ立って動かないと、大型台風でぽきっと折れることも。
一方、ゆらゆらと柳のように雨風に揺れながらも、無理せずしなやかに生きること、大事な生きる術だと思います。
こんなこともあります。
明らかに仕事や役割が過剰で、これ以上はキャパオーバーなのに本人が心の声を無視し続けたら何か小さなことをきっかけにばたっと倒れてしまう…

その子にとって学校環境が厳しく、対人関係も過酷。
でも誰にも打ち明けることができず、小さなことをきっかけに頑張りの糸が切れてしまう…
何らかの理由で、もうこの会社では働き続けられないと思いつつ、心がや感情がマヒしてしまい現状続行以外の選択肢を持てない。
身体がボロボロになって悲鳴を上げてやっと気づく…
どの場合も何がワラ1本だったんだろうと考えてしまいます。
と同時に、周りの人が気づき、風で飛んでくるワラを手で払ってあげることができたら、その人はひと息つけて、自分の本音に気づき人生に対して新しい見方、別のアクションが取れるのではとも思いました。
周りを見回して、頑張ってるラクダさんがいたら、お茶にでも誘って話を聞いてみましょうか。
2025.7.25
Romi