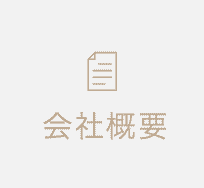私は未だに”あのベストセラー「世界がもしも100人の村だったら」の原文を訳して日本に紹介した人”といっていただくことがあります。
皆さんも「100人の村」を覚えていらっしゃいますか?
あのメッセージが元世界銀行の同僚から日本にいる私に送られてきたのが2001年の3月7日。
すべてはそこから始まりました。
そして「100人の村」が日本中一気にブームになったのは、もう20年も前のこと。
学校の教材にも取り上げられたようです。

20年前とは確かに数字やデータは全く変わりました。
人口も当時の60億人から今や81億人といわれています。
でも、人間は未だに“競争と対立”のゲームから足を洗うことができません。
今世界で起こっている不平等、考え方の相違からの対立は、これまでとは全く違う新しい世界観を持って乗り越えていくときに来たと思っています。
ブームから時が経ち、私はあの「100人の村」をどう読み解くかという本を出版しました。
もう絶版になってしまったのですが、今読み返すとまさに…というところがあるので、ここに少し引用してみますね。
⚫️100人の村と考える種(ビジネス社 2010年)
ー前書きから抜粋ー
最近何かが違う…と気づいていますか?
過去の歴史、社会データをどれだけしっかり分析しても、その延長線上に未来を予想しても、もう間に合わないのです。
政治、経済、自然環境、医療、教育、福祉…あらゆる分野でその変化が現れています。

今まで有効だった社会常識を振りかざしても、それに対する反応は今までとは違い虚しく感じられるかもしれません。
その時代に生きる人が共有する考え方の枠をパラダイムといいますが、そのパラダイムを大きく変化させなくてはならない大切な時期にきています。
「過去の延長上に未来は作れない」ということは、開き直るとこれからの世界は私たちの想いで自由に、豊かに創っていくことができるということなのです。
私は経済専門家でも、社会派ジャーナリストでもありません。
専門性に関しては、その道のプロにお任せするとして、生きているなら誰でもが“人間のプロ”といえます。
人間のプロとして今の世界を見るといちばん肝心なことが抜けていると思います。
それはBe Happy「人生は楽しむためにある」ということの認識です。

「世界がもし100人の村だったら」
を読むと、世界中の人たちを経済的・物理的に豊かな順番に並べたら、現代日本のほとんどの人が上位25%、それどころか、上位8%に入るということになります。
一方で、現代日本では自ら命を終わりにする人が年間3万人、それがここ10年以上も続いているという現実。
これが物語っているのが、経済的・物理的豊かさイコール幸せではないという事実。
私が世界銀行本部に赴任した当初、同僚から言われたことを思い出します。
「日本は世銀が設立された50年ほど前(設立は1945年)は世銀から借り入れで復興を成し遂げた国。それが今では経済大国として、アメリカに次いで2番目の世銀への資金提供国(注:当時)。それは驚くべきことだ。その成功の秘訣は何だと思うか?」と。
母国日本は凄いことを成し遂げた国なんだ、と当時は誇らしく思ったものです。
西洋の経済学者が驚くようなことを成し遂げる力が日本人にはあったのですね。
そういえば初めて日本を出て、英国での生活を始めた1970年頃、あちらで目にする「Made in Japan」は、確かに安価でローテクで技術のいらない壊れやすいもの、誰も特に欲しがらないような単なる土産物の代名詞でした。
その同じ「Made in Japan」が日本の復興に伴い短期間でどんどん価値が増し、今では高価で、ハイテクで、ステータスシンボル。
誰もが手にしたいと思うようなものに変わったのです。
しかし、その経済の成功の裏で何か大切なものを置いてきてしまった感があります。

過去ではなく、今の話をしましょう。
今をどう生きるか、それが大切なのです。
何か大切なものを忘れてきた…といっても、その期間は長い人類の歴史からすれば、ほんの瞬きする間の話、取り戻すことはできるのです。
あの「100人の村」ブームから約10年経った今、新しい世界観の観点から、このメッセージを読んでみると、またとても深いものがありました。
そしてそこには今の閉塞感を打破する知恵がありました。
それも政治の仕組みや世界経済の動向に流されるのではない、個人個人が自分の考え方を見直して、新しい世界観を身にまとい、幸せというエネルギーを、日々の中に取り込むための生き方のヒントがあったのです。
ー抜粋終わりー
この本のあとがきには、今、私たちが個人個人として取り入れられる考え方のヒントがいくつも書いてあります。
次回はそれについてお話ししようと思います。
Be Happy!
2025.3.14
Romi