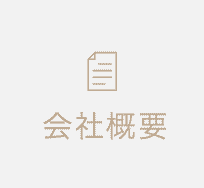昔々、あるところに、、
カエルの集団が森の中を新しい土地を求めて大移動していました。
気がつくと、仲間の数が足りないことがわかりました。
みんなで探しに戻ってみると、草むらの中に大きな穴があり2匹が間違ってその穴に落ちてしまっていたのです。
みんなは穴の周りに集まり、大声で声をかけました。
「大丈夫か〜」
「ジャンプしてここまで上がっておいで」
「そうそう、がんばれ、がんばれ」
穴の周りに集まった仲間のカエルたちは口々に声を張り上げます。
その声に応えるように2匹のカエルは気を取り直し、地上に向かって飛び上がります。
しかし、穴は思ったより深くジャンプで届く距離ではありません。
でもみんなは声援を送り続けます。
「もうちょっとだ、ガンバレ、僕たちは君たちを見捨てないよ」
2匹のカエルたちはあちこちに体をぶつけ傷つきながらもジャンプを止めませんでした。

大切な仲間です。
置いていくわけにはいきません。
穴の周りのみんなも一生懸命応援し声も枯れてきました.
2匹は満身創痍でジャンプし続けました。
惜しい、もうちょっとのところでまた奈落の底に落ちていきます。
日もどっぷりくれた頃、いつの間にか1匹のカエルは穴の底で動かなくなってしまいました。
一方、もう1匹のカエルは落ちても落ちてもまだジャンプをし続けています。
飛び上がっているのはもう1匹しかいません。
そして何かの拍子に穴の途中で、もう一度ジャンプする場所を見つけ、必死の力で飛び上がったところ、奇跡的にも穴の淵に手がかかり、穴の外に出ることができました!
みんな大喜び。
生還を喜び合いました。
さて、
穴の下で冷たくなってしまったカエルと体が傷だらけになりながらもどうにか飛び上がって助かったカエル。
この2匹の違いはどこにあったのでしょう?
それは
1匹は普通のカエルで、もう1匹は全く耳の聞こえないカエルだったのです。
助かったのはどちらのカエルだったと思いますか?
この話をアメリカで友人から聞いたとき、私はすぐに耳が聞こえたカエルにみんなの声が届いたから助かったんだなぁと単純に思いました。
ですが、友人の答えはその反対でした。
助かったカエルは全く耳が聞こえなかったというのです。
耳の聞こえるカエルはいつの間にかジャンプを諦めて、穴の底で冷たくなっていきました。
はて?
それは穴の周りの仲間のカエルたちの変化でした。
当然、最初はみんな大きな声で声援を送り励ましました。
「もうちょっとだ、頑張れ!」
「こっちに向かって飛び上がったほうがいいよ。」
「もう少し横からトライして!」
口々に現状打破のためのアドバイスを送り続けます。
ところがしばらくして現実が見えてきます。
状況を客観的に俯瞰して見て穴の上のカエルたちの気持ちが徐々に変わっていきました。
「もうダメだ、無理だよ。」
「そんなに体を痛めつけることはない。静かに休め。」
「もう地表に上がるのは無理だ。」
「諦めて。もう静かにしたほうがいい。」
「僕たちは決して見捨てない。いつまでも一緒にいるから、もう無駄な努力はやめにしよう。」
みんなの頑張れ・励ましコールは、もういいよ・無理をしないでコールに変わっていったのです。

耳の聞こえるカエルはそれがリアルタイムで全て聞こえていました。
そしてみんなが言うことを現実として捉えてしまいました。
そしてその通りになっていきました。
ところが、
耳が聞こえなかったカエルは穴の底から見上げると、みんなが口々に応援してくれているように思えたのです。
みんなの口パクがずっと応援と励ましと解釈していたのです。
みんなが言ってることが聞こえなかったからこそ、希望をあきらめませんでした。
みんなの声が届かなかったからこそ、みんなのアクションを励ましと思い込むことができました。
どうでしょう?
意外な展開でしたか?
実はこのカエルの話、現実の世界でも起きていることだとは思えませんか?
何かトライしてダメだった場合、周りの人の意見を聞きすぎて諦めているかもしれませんよ。
でも、それには耳をかさず、自分を信じてとにかく飛び上がり続けること、その思いが奇跡を生み出すのですね。
外にいた仲間たちも強い友情で支えていました。
でも現実を客観的に見ているうちに“無難な答え”に行き着いたのです。
・ダメなものはダメだ。
・無駄な抵抗はよそう。そしてこれも自分の運命と受け入れよう。
・ときには妥協も大切。
・そんなに無理をすることは無い。
確かに一理あります。
がんばりすぎてズタズタになる前に状況を俯瞰して考えてみることは必要です。
でも、
今考えると、他にもいろいろチョイスがあったと思うのです。
例えば上に上がろう上がろうとするのではなく、穴の底をぐるぐる回りながら別の逃げ道を探すという手もあったかもしれません。
上にいるカエルたちも、近くを探して、折れた木の枝を穴の中に落とし込んで、飛び上がりの台を作るということもあったかもしれませんね。
いろいろ考えさせられる現代のおとぎ話、でした。
2024.9.27
Romi