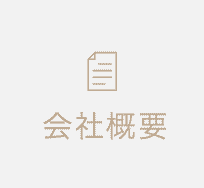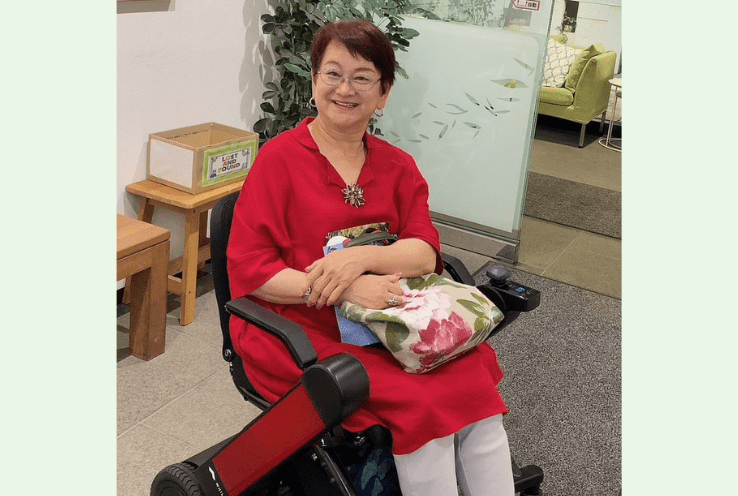世界的気候変動は各地で驚くべき現象をもたらしています。
昨年は地球温暖化を通り越して“地球沸騰化”という新しい言葉が生まれましたね。
今年の日本ではいつもなら「暑中お見舞い」が「猛暑お見舞い」になり、日本列島どこも沸騰している感じがします。
長かった梅雨が明けた途端、暑い日が続いて毎日各地の様子がニュースを賑わしていますが皆様、体調は大丈夫ですか?
家の中にいても熱中症になる、なんて昔は考えられませんでしたが、毎日救急車が大忙しですね。

先日、友人がFacebookに
以前、私の講演会で聞いた話として「真夏のインド人」を投稿してくださいました。
とっても懐かしく思い出しました。
そこでもう一度この話をさせていただきますね。
以前アメリカの国際機関で働いていたときの同僚のインド人女性エルフリーダとの会話です。
彼女は少し前に日本に出張に行って帰ってきたばかりでした。
日本がいかにきれいで、人が親切で、全てが効率よくできていて快適だったか話してくれました。
それを聞いてとても誇らしく思いました。
加えて朝の通勤時間の山手線のホームの話を驚いた表情で熱く語ってくれました。
「ホームには印があって、3列に並んでいるの。電車が来るとドアは寸分違わずその3列のところにきちんと停止。
それにも驚きだったけど、その3列の人たちが電車に吸い込まれていった後がもっとすごかった。その横に並んでいた3列の人々が黙って横に移動して次の電車を待つのよ。
まるで軍隊か運動会の練習のよう。
こんなふうに乗る人も電車の停車位置もきちんとしてるから、日本の鉄道は遅延がないのでしょうね。
そして東京の人々の歩くスピードの速さに私は度肝抜かれたわ。とにかく早い!
目的地に向かってまっすぐ行進しているかのよう。
なんでそんなに急いでるのかしら?私の国ではね…」
と話し始めたのが「真夏のインド人」というストーリーに繋がるのです。

彼女によると、インドはとにかく灼熱の太陽の土地なので、夏の昼間、外を歩くだけでも体力の消耗は大きい。
だから人々は日中はほとんど出て歩かない。
そして夕方になって、やっと動き出すが急いでたくさんのことをこなすというわけではなく一つ一つゆっくりすることになる。
だからのんびりしてるように見えるけれど、あれは体力を温存するための生きる知恵だということでした。
確かにその頃の日本は夏といっても今のような猛暑ではありませんでした。
30度超えたら話題になる位で、今は40度に近くなったと大騒ぎしています。
たったこの20年のことだというのに。
また、大都市東京では、人々の歩くスピードはとても早い、とはたまに上京する人からも聞くことがあります。
目的地に向かってすごい勢いで無駄のないように歩き、仕事をし、あらゆることをこなす。
勤勉で効率重視の国民と言われても当然だと思います。
かくいう私だって若い頃はそういう効率を求める一人でした。
一つのことをやりながらも、次のことを考え、できれば二つ三つのことを同時にこなして今日のスケジュールをきっちり終わらせよう、なんて考えていました。
それって馬車馬かロボットのようですよね。
日々を味わう。とか何気ない日常の会話を楽しむ、とか四季の移り変わりを感じる、、、そういうものはみんなすっ飛ばして歩いてきたような気がします。

同僚のインド人、エルフリーダの東京見聞録の話を聞きながらそんなにきっちりと効率よく全てをこなすことが必要なんだろうか、と考えてしまいました。
今、日本でもマインドフルネスという瞑想法が認知され、忙しい会社でも社員のケア、福利厚生に積極的に取り入れられてきています。
目を閉じて、心に波立つ感情をスッと流し、今、ここにいる自分にだけに集中すること。
また1杯のお茶をいただく、その所作に心を込めて、ゆっくり味わい。
そして少しずつ喉を通していく。
こういうことが心穏やかにする方法として紹介されています。

私は10年前に脳卒中で倒れたことにより、それまでの忙しく、効率よく立ち振る舞う生活に強制終了がかかり、自然に生活のペースをゆっくりせざるを得なくなりました。
今その生き方が私に大きな幸せをくれています。
もっと!もっと!早く!早く!と始終耳元でささやかれているような生活、あのまま行ったら今頃潰れていたのではないかしら?
目の前のことをゆっくりこなしていく生き方、まさに真夏の直射日光を避けて体力を温存しているゆっくり歩くインド人の姿がダブりました。
自分の体調を気遣いながら目の前のことに心を向けてそれをゆっくり味わい愉しむ、そんな生活を取り戻したいと思います。
真冬でも、インド人じゃなくても「真夏のインド人」ライフ、ぜひ取り入れてみてください。目に見える景色が変わってきますよ。
2024.7.30
Romi